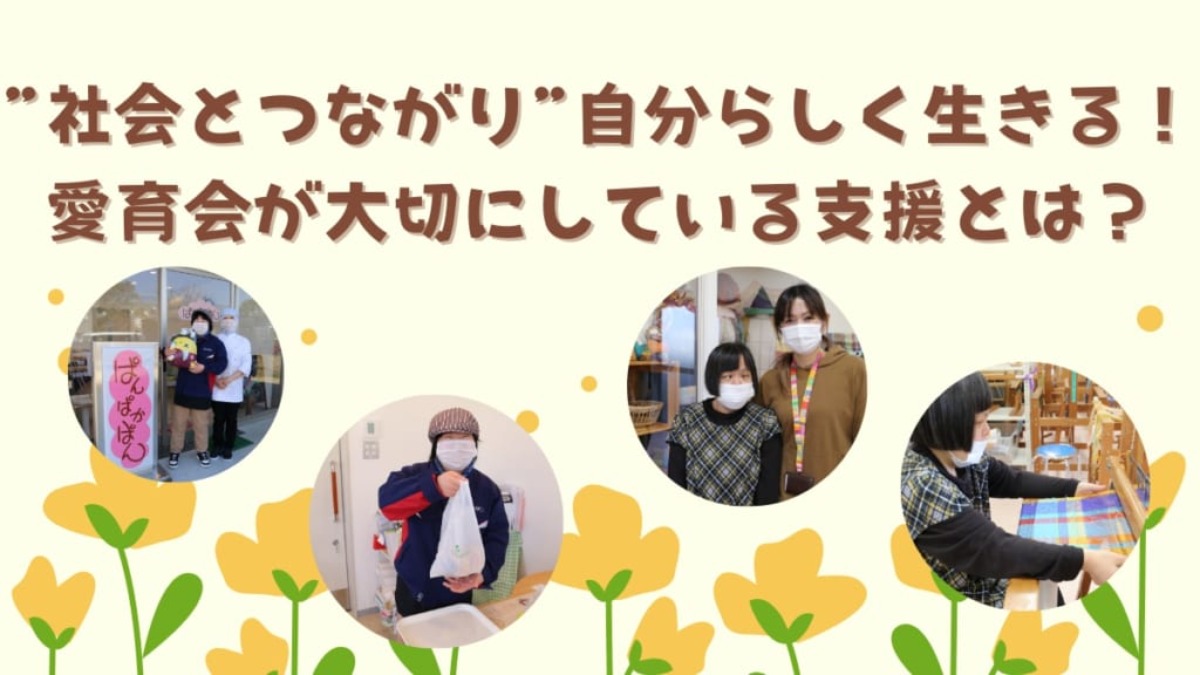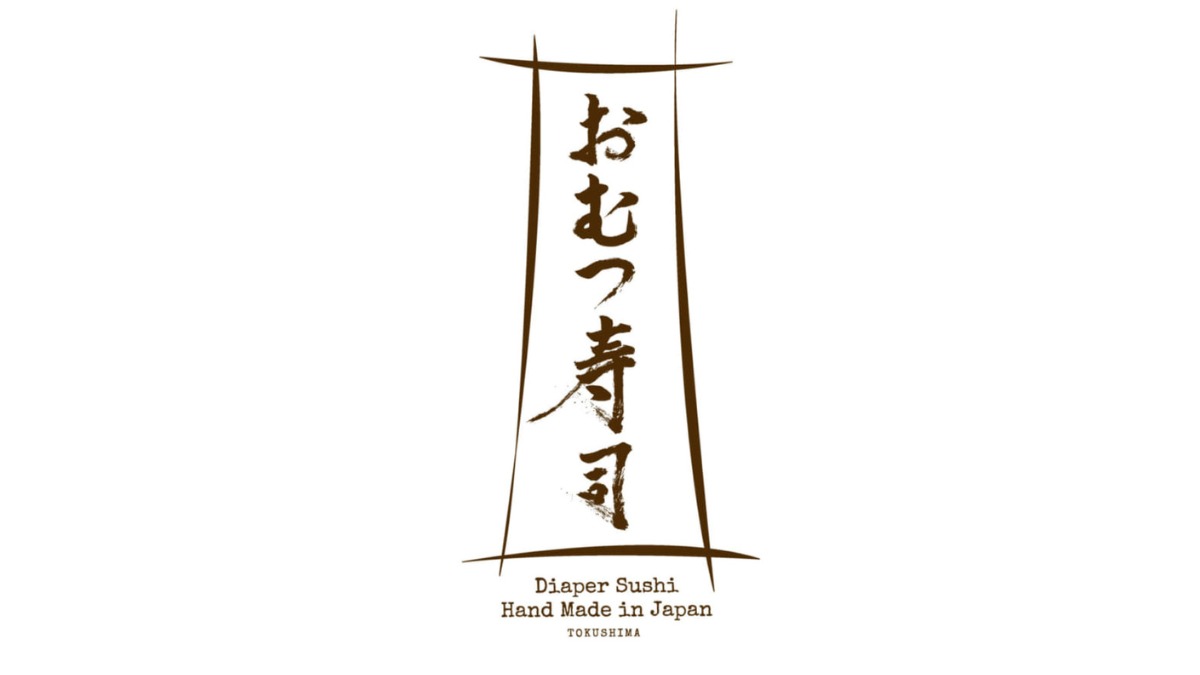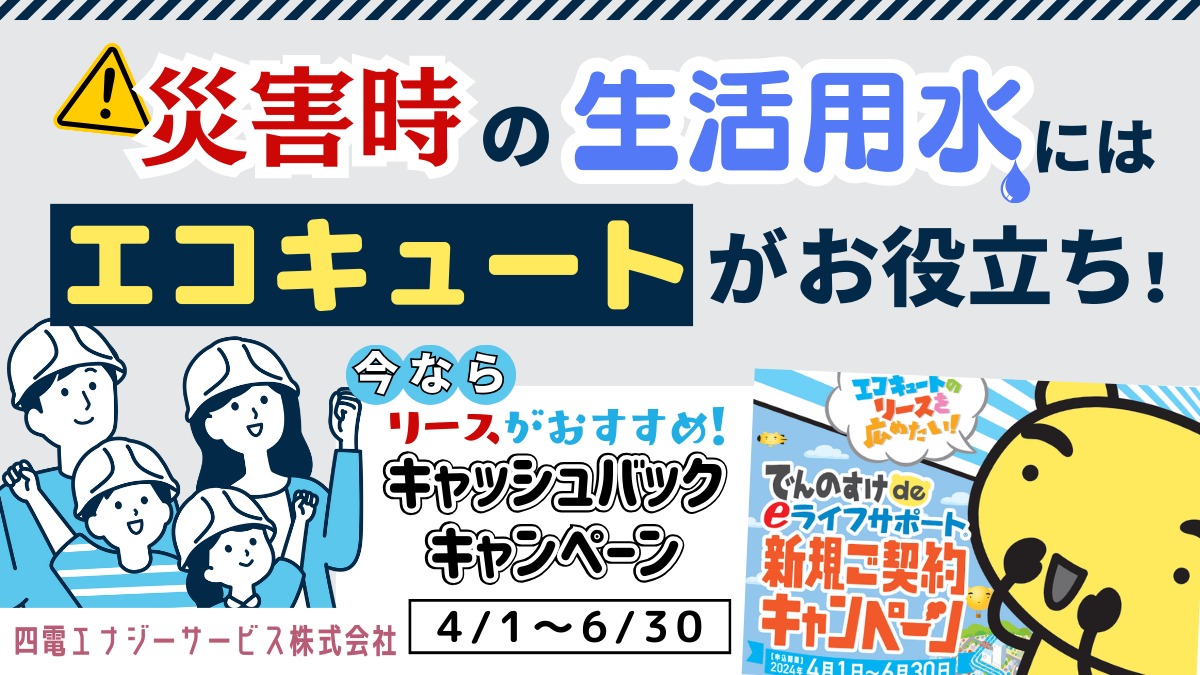2020/04/14 14:13
あわわ編集部
【大麻町特集】熟成期間1年以上!?絶品醤油を作る福寿醤油は194年続く超・老舗蔵だった!
| 鳴門海峡の渦のまち・鳴門市の西部に位置する大麻町。 古社寺が点在する、古くから信仰の聖地であり、お接待で培われた人情味が溢れる町です。 そんな大麻町には、大谷焼をはじめとした、 さまざまな体験施設が並んでいます。どれも、大麻町でしか楽しめないものばかり。 そんな大麻町の体験施設を徹底取材します。 |
大麻町といえば、風情豊かな街並みが魅力。
その中でも、特に印象的なのは隣り合う酒蔵と醤油蔵。
今回は、古くから続く蔵のひとつ『福寿醤油』さんに行ってみました。
今回、見学してくれたのはこちらのふたり。

昨年のミスコン紹介記事にも出てくれた東條さんと東さん。どちらも栄養士を目指して勉強中!
こちらもチェック!→【連載】徳島県内3大学ミス&ミスターコンテスト事前特集/徳島大学 蔵本キャンパス・ミスコン編
東條さん:
東さん:

迎えてくれたのは福寿醤油9代目であり、代表取締役でもある松浦亘修さん。
大学卒業後、不動産会社や派遣会社の営業マンを経て30歳の節目を期に家業を継ぐ。
食育の一環で『しょうゆ もの知り博士』として小学校を訪れ、
出張授業などをおこないながら、醬油の啓発に努めています。
松浦さん:
東條さん:
松浦さん:
東さん:
松浦さん:

栄養学の知識はバッチリなふたり
松浦さん:
東條さん:
松浦さん:
東さん:
松浦さん:

風情溢れる蔵内を歩くだけでも楽しい
松浦さん:

松浦さん:
東條さん:
松浦さん:

どーん!入れ物いっぱいにぎっしり詰まった小麦&大豆
東條さん:
松浦さん:

だいたい1日目の麹
東さん:
松浦さん:

すごい熱気で曇っていますが、こちらが3日目の麹
松浦さん:
東さん:
松浦さん:

巨大なプールにたっぷり!落ちないように気をつけて!
松浦さん:
東條さん:
松浦さん:
東さん:
松浦さん:
東條さん:
松浦さん:
東さん:
松浦さん:

東條さん:
松浦さん:
東さん:

松浦さん:
東條さん:
松浦さん:

麹作りに仕込み、圧搾・・・時間と手間ひまをかけて作られているんだなぁ。

この後も、火入れや味付け、出荷にいたるまで色々教えていただきました!
松浦さん:
東さん:

福寿醤油、自慢の6種類をテイスティング!
松浦さん:

松浦さん:
東條さん:
東さん:

種類がわかったところで、いざテイスティング!

松浦さん:

東さん:


東條さん:


気づけば醤油ワールドにハマったふたり。実家へプレゼントする醤油を選んでいました。
文政9年から脈々と受け継がれる醤油づくり。
そこには、先代の思いと“おいしい醤油を作りたい”という、
9代目の思いがありました。
大量生産とは反対をいく福寿醤油の醤油は、
ぜひ醤油蔵を見学して、味わってみてください。

福寿醤油の商品は直売所や県内スーパー、お土産ショップなどで販売中。ネット通販も可能。
醤油蔵見学
| 営業時間 | 月~土 9:00~17:00 |
| 見学所要時間 | 約30分※見学後は醤油のテイスティングあり |
| 予約制 | 要予約 |
| 料金 | 無料 |

醤油蔵の外にある使い終わった大きな樽と記念撮影(笑)!
まだまだあります、大麻町特集!
【大麻町特集その①】採れたて絶品しいたけに感動!サンコウファームしいたけ狩りにいってみた
【大麻町特集その②】ご先祖は〇〇!?お酒好き3人組が“徳島最古の酒蔵”本家松浦酒造で蔵見学!
【大麻町特集その③】オトナ女子も陶芸がした~い!大谷焼 元山窯ではじめての電動ろくろ体験!
【大麻町特集その④】徳島が誇る伝統工芸・大谷焼! 創業140年・矢野陶苑で“ねって、こねって”手びねり体験
【大麻町特集その⑥】森陶器で電動ろくろ体験やってみた!国登録有形文化財の登り窯&水琴窟も必見
【大麻町特集その⑦】家族みんなで陶芸体験するなら窯元・大西陶器へ!絶対買いたい最新アイテムも発見♪
【大麻町特集その⑧】大谷焼づくりは超ハード!?自分だけの器を目指して梅里窯で手びねり体験
【大麻町特集その⑨】元気いっぱい3兄弟が佳実窯で大谷焼体験!電動ろくろ&絵付けに挑戦
福寿醤油株式会社
- 住所/ 鳴門市大麻町 池谷大石8
- 電話/088-689-1008
- 営業時間/8:30~17:00
- 定休日/日
- 駐車場/有